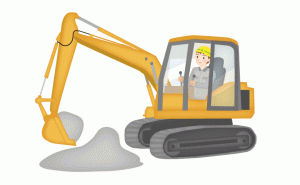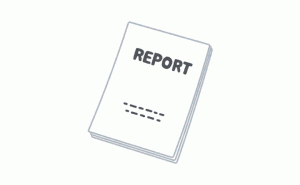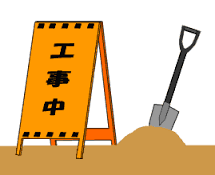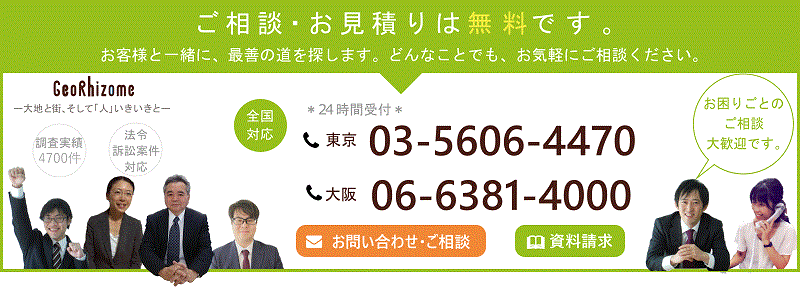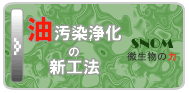こんにちは!
残土条例や残土調査など、土壌汚染対策法の調査契機によらない土壌汚染調査についてのお話についてお話します。
土壌汚染対策法は法律ということで国が定め、運用されているものですが、条例は都道府県が定め運用されている制度です。
その一つを紹介致します。
静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)
*この条例については、私自身まだまだ勉強中の為、間違いがあった場合には訂正させていただきます。ご了承ください。
静岡県盛土条例が制定された経緯としては、令和3年7月に起こった熱海の土石流災害が不適切な盛土を起点とする、土石流が発生したことに由来します。
簡単に盛土条例の中で土壌汚染に関係する部分について説明しますと。
■申請前
盛土工事を行う土地において、土砂基準(土壌汚染の基準)に適合する土壌であるかを調査が必要。
■許可後(盛土工事期間中)
①盛土材料が土砂基準(土壌汚染の基準)に適合する土壌であるかと調査が必要。
②定期的(6ヶ月に1度)に施工中の盛土による土壌汚染を把握するため、
土壌及び水質の調査を行ない、調査結果を報告する。
■完了時
盛土工事完了後に盛土による土壌汚染の影響を確認するために、
土壌及び水質の調査を行ない、調査結果を報告する。
実際の調査方法については、土壌汚染対策法よりも残土条例の調査方法に近いという印象ですね。ただ、残土調査にはない、水質の調査が必要な様子です。
まだまだこれは勉強中なので、はっきりと調べ切れていないのですが、水質の調査については、果たしてどこから採水するの?という疑問があります。
平地であれば既存の井戸などがあるように思うのですが、山間部の盛土を行う工事の場合、距離が離れていても既存の井戸で調査を行なうの、はたまた井戸を新設するのか・・・。
井戸を新設するとなるとかなり費用が掛かる印象ですね。
水が出てくる深度にもよりますが、1箇所当たり40万円以上はするのではないでしょうか・・・。
また勉強し判明次第、アップデート致します。
土壌汚染の分野でも、新しい情報や条例が出てきます。これからもまだまだ勉強が必要ですね。
ジオリゾームでは土壌汚染対策法や条例など新しい情報について社内勉強会を開催し、アップデートしています。
土壌汚染調査について、費用や調査方法など、ご不明なことがありましたら、
お気軽にジオリゾームまで、ご相談下さい。
森上
2022年7月2日更新
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
みなさんこんにちは!
建設工事をする際には残土というものが出ます。
今日はその残土について少しお話ししたいと思います。
残土とはいわゆる建設発生土のことで、建築工事及び土木工事などで建設副産物として発生する土のことです。
その残土を処分する際に残土を受け入れる所があるのですが、近年ではその受け入れ先から持ち込む残土について土壌調査をするように言われることが多くなっています。
自治体によっては条例によって残土の調査が義務付けられている場合もあります。
その際に分析する項目としては土壌汚染対策法で定められている特定有害物質であることが多くなっています。
+αでそれ以外の物質も調べる場合もあります。
自治体や残土の受け入れ先によって試料の採取方法や分析項目も変わりますので、残土の調査でお困りのことがあれば、是非ジオリゾームまでお問合せ下さい!
森上
~~~~~~~~~~~~~2020年7月15日追記~~~~~~~~~~~~~~~
土壌汚染対策法と建設発生土などからみられる土壌汚染についてお話いたします。
土壌汚染対策法では、有害物質が使用されていた工場が廃止する場合等に行われる土壌汚染対策法の【第3条調査】。3000m²以上の土地の掘削や盛土を行う際に行われる【第4条調査】があります。これらを【義務調査】と言います。他には土地売買などで土壌汚染の有無を判断するために行われる【自主調査】があります。
【義務調査】【自主調査】何れの調査におこる人為的な土壌汚染を把握するための調査です。土おいても、基本的には産業活動などから引き壌汚染調査の考え方としては、薬品など土壌汚染を引き起こしてしまう有害物質を床にこぼしてしまったり、配管からの漏洩による土壌汚染が無いかを調査します。そのため、まず最初に土壌を採取する場所としては、地表面や配管付近から土壌を採取することになります。地表面や配管周りから土壌汚染が検出されなければ、調査を行なった敷地は土壌汚染が無いと判断することになります。
同じように土壌汚染を調べるということについて、工事などで掘削を行う際に出てくる建設発生土の土壌汚染を調べる調査というモノがあり、業界では残土調査と言われております。残土調査と土壌汚染調査の違いについてご説明します。
土壌汚染調査は土壌汚染対策法に則り調査を行ないます。法律となりますでの、国が定めた基準です。残土調査は、残土条例という各都道府県が制定している条例が基準となります。さらに、残土調査は残土を受け入れる処分会社によって土壌を採取する方法や有害物質の分析などの試験項目が異なります。
大まかに言えば、土壌汚染対策法の有害物質と同等の内容となっているケースもあるのですが、1.4-ジオキサンや油分、水素イオン濃度など、土壌汚染対策法では定められていない項目について調査が必要なところもあります。
調査の密度も土壌汚染対策法では土壌汚染のおそれ(≒可能性)が高いと判断される場所では100m²当たりに1地点での試料採取となりますが、残土条例では掘削する土の量で定められており、3000m³毎であったり、4000m³毎、5000m³毎など処分場の方針に沿う形で調査を行なわなければなりません。
ジオリゾームでは残土条例の調査経験も豊富にございます。
土壌汚染調査だけではなく残土条例についても詳しくお話を聞きたいなど
ご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
森上
■□関連□■
各都道府県の条例一覧
土壌汚染対策法とは?
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。